■ 毎日の「いただきます」の向こう側
毎日のように、「ごはんできたよ」と子どもを呼ぶ。
テーブルには、お米、味噌汁、野菜のおかず。
でも――その一皿がどこから来たのか、意識したことはありますか?
今の時代、食べ物はお金を出せば簡単に手に入ります。
スーパーに並ぶ野菜や肉、加工品。スマホ一つで宅配も頼める。
でもその便利さの裏で、“作る人”の存在がどんどん見えなくなっていることに、
私たちは気づかなくなっているかもしれません。
■ 農業は「命を育てる仕事」
農業は、単に作物を育てるだけの仕事ではありません。
土を整え、種をまき、天候と向き合いながら、
**“食べ物になるまでの命のプロセス”**を、日々支えてくれている仕事です。
たとえば、お米。
私たちが炊飯器で炊く前には、
何ヶ月ものあいだ、水の管理、害虫の駆除、雑草との戦いがある。
それは自然との対話であり、丁寧な手仕事の積み重ねです。
野菜も同じ。
「曲がってるから」「色が悪いから」と弾かれるものの中にも、
人の想いと手間が詰まっています。
食べ物は、命そのもの――それを育てる農業は、まさに“命をつなぐ仕事”です。
■ 農業の現実:支える人がいない
日本の農業の現実は、なかなか厳しいものがあります。
農家の平均年齢は67歳を超え、後継者がいない地域も多い。
そして、農業で生計を立てることが難しいため、若者は別の道を選びがちです。
けれど、「食」がなければ、生きていけない。
私たちは日々、誰かの“育てる力”に支えられて暮らしているのに、
その人たちがいなくなろうとしている――これは、まさに暮らしの根っこが揺らいでいるということではないでしょうか。
■ 「農にふれる」は子育てにこそ必要な体験
今、都市でも増えてきているのが、農業体験や家庭菜園。
たとえ一時的でも、土に触れ、野菜が育つ過程を体験することで、
子どもたちは多くのことを学びます。
・土に手を入れる感覚
・時間がかかることの意味
・待つこと、失敗することの大切さ
・「食べる」ことの重みと喜び
大げさに言えば、それは生きる力の土台づくり。
親として、「安全で安心なものを食べさせたい」という想いがあるなら、
その背景にも、きちんと目を向けていきたいものです。
■ 自分の子どもが将来“農に関わる”未来を想像する
もし、あなたの子どもが将来こう言ったらどう感じるでしょう?
「農家になりたい」
「畑をやってみたい」
「自然の中で暮らしたい」
それは、今の時代には**“遠回りに見える”選択肢**かもしれません。
でも、本当にそれは“後ろ向き”でしょうか?
むしろ、これからの社会に必要なのは、
“つくる人”“支える人”を増やしていくことなのではないでしょうか。
農に希望があると思える社会にするには、
親世代の関心が、第一歩になります。
■ 最後に:未来の食卓は、今の暮らしから始まっている
私たち親が毎日用意する食卓は、
未来の社会の縮図のようなものかもしれません。
-
何を選ぶか
-
どこから来たものかを知るか
-
誰が作ったのかを想像できるか
「食べること」は「生きること」。
その重みを子どもに伝えるために、
まずは私たち自身が“農のこと”にもう一歩近づいてみませんか?
🍙 もし、農や食のことで気になることがあれば
お米、野菜、自給のこと、農業体験の場……
何か困っていたり、知りたいことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
小さな関心が、大きなつながりの第一歩になるかもしれません。


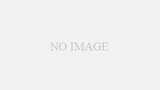
コメント