「過去は関係ない」「人は変われる」——こう言われたら、あなたはどう感じますか?
これは、オーストリアの心理学者アルフレッド・アドラーの考え方に基づく「アドラー心理学」の基本的な姿勢です。
一時期ベストセラーとなった『嫌われる勇気』を通じて、多くの人に知られるようになったこの心理学は、今の自分を肯定しながら、未来に向かって前向きに生きるためのヒントがたくさん詰まっています。
今回は、「アドラー心理学って何?」「どうやって役立てるの?」という疑問にお答えする形で、わかりやすく解説していきます。
アドラー心理学とは?
アドラー心理学は、20世紀初頭に活躍した心理学者、アルフレッド・アドラーによって提唱された心理学の一派です。
他の心理学が「過去のトラウマ」や「無意識の衝動」に注目したのに対し、アドラーは**「人は今、どのような目的を持って行動しているか」に注目**しました。
つまり、「なぜそうなったか?」ではなく、「これからどうしたいのか?」を重視する未来志向の心理学なのです。
アドラー心理学の基本3原則
1. 目的論:「人は目的に向かって生きている」
アドラー心理学では、「人は原因ではなく、目的によって行動する」と考えます。
たとえば、「私は人見知りだから友達ができない」のではなく、
「友達をつくることで傷つくのを避けたいから、人見知りという態度を選んでいる」と考えるのです。
つまり、「できない理由」は「やらない目的」の表れだという視点。
この考え方は、現状を自分の意思で変えていける可能性を示してくれます。
2. 課題の分離:「自分の課題」と「他人の課題」を分ける
アドラーは「人間関係の悩みのすべては、他者との関係に由来する」と言っています。
そこで大切になるのが**「課題の分離」**という考え方。
-
「自分がどうするか」は自分の課題
-
「他人がどう感じるか」「どう評価するか」は他人の課題
たとえば、
「親が自分の進路に反対する」→これは親の課題であり、自分の課題ではない
「友人にどう思われるか心配」→それは友人の課題であり、自分が操作できるものではない
こうして線引きをすることで、人間関係に振り回されず、自分の人生を主体的に生きることができます。
3. 共同体感覚:「人はつながりの中で生きている」
アドラー心理学では、**「自分の価値を他者とのつながりの中で実感すること」**がとても大切とされています。
この「共同体感覚」は、
-
自分には居場所がある
-
誰かの役に立てている
-
つながりを感じている
という感覚を育てていくことです。
つまり、競争ではなく、貢献を軸に生きる姿勢。
この感覚があると、孤独感が薄れ、生きやすくなります。
アドラー心理学を日常に活かすには?
では、どうすればアドラー心理学を日常に活かせるのでしょうか?
簡単なステップを紹介します。
◎ 「できない」のではなく「やらない理由は何か?」を考えてみる
何かを避けているとき、「なぜ避けたいのか?」を考えてみましょう。
自分の行動が何を守るためのものなのかが見えてきます。
◎ 他人の評価を手放す
「どう思われるか」ではなく、「自分がどうしたいか」に意識を向けましょう。
他人の課題を背負いすぎないことが、自分らしい生き方につながります。
◎ 誰かのためにできることを探す
「ありがとう」と言われる経験を積み重ねることで、自分の存在価値を感じやすくなります。
特別なことをしなくても、挨拶をする、話を聞く、それだけでも十分です。
まとめ:変われるかどうかではなく、「変わると決める」こと
アドラー心理学の魅力は、「人はいつからでも変われる」という前向きな視点にあります。
「誰かに認めてもらうために生きる」のではなく、
「自分の意思で、自分の人生を選んで生きる」
そんな力強さと優しさを、アドラー心理学は教えてくれます。
もし今、迷いがあったり、誰かに振り回されて疲れているのなら、
ぜひ一度アドラーの考え方に触れてみてください。
あなたの人生のハンドルは、あなたの手にあるのです。

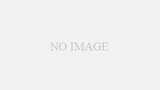
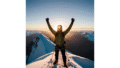
コメント